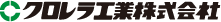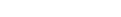春の不調対策 ―自律神経の整え方―
春は寒暖差や気圧の変化が大きく、自律神経が乱れやすい季節と言われています。
なんとなく疲れやすい、寝つきが悪い、気分が落ち込みやすい…そんな不調に心当たりのある方も多いかもしれません。
新生活のスタートを迎える方も多いこの季節。大事なイベントに備えて心身のコンディションを整えるために、小さなステップから始められる“自律神経”へのアプローチをご紹介します。

自律神経とは
自律神経は私たちの意思とは無関係に働き、24時間常に身体の機能を調整しています。
交感神経と副交感神経の2つが拮抗して働いており、体温の維持や呼吸、発汗、消化など、生命の維持に必要な様々な働きをコントロールしています。全身に血液が流れているのも、胃腸で食べ物の消化吸収が行われるのも、眠っている間に呼吸が止まってしまわないのも、私たちが意識してもできない身体の働きはすべて自律神経のおかげで機能しています。
交感神経
日中起きているときや緊張しているときに優位になる神経です。
心拍数を上昇させたり発汗を促進させ、逆に胃腸の動きは抑制されます。
副交感神経
寝ているときやリラックスしているときに優位になる神経です。
呼吸が深くゆっくりになり、栄養素の吸収や排泄などの胃腸の動きは活発になります。
自律神経は通常一定のリズムで働いており、本来は朝~日中にかけては交感神経が優位に、夕方~夜にかけては副交感神経が優位になります。しかし、強いストレスや昼夜逆転の生活などが続くと、この2つの神経のバランスが崩れてしまいます。自律神経は全身に張り巡らされており、自律神経の乱れによって現れる症状は人それぞれ。不眠、頭痛、動悸、便秘などの消化器症状、不安感、イライラなど…症状の種類も身体、精神面ともに多岐にわたります。
季節の変わり目は、自律神経の乱れによる体調不良を起こしやすい
季節の変わり目、特に春に生じやすい不調の原因はさまざまです。
気温差
春は暖かくなったと思えば急に寒さがぶり返すこともあり、気温の変動が激しい季節です。この気温差に対応するために体温調節を頻繁に行う必要があり、エネルギーを通常よりも多く消費してしまいます。その結果、疲れを感じやすくなることも。
日中と朝晩の寒暖差に備え、重ね着などの工夫を上手に取り入れ、こまめに調整できるようにしておきましょう。
気圧の変化
春は低気圧と高気圧が頻繁に入れ替わり、気圧の変動が大きくなります。気圧の変化は自律神経にも影響を与え、頭痛やめまい、倦怠感などの体調不良を引き起こすことがあります。
天気の変化をチェックし、身体の不調を感じる場合は無理をせず適度に休息を取ることが大切です。
ストレス
春は特に、進学や進級、就職、異動などのライフイベントが多い時期でもあります。環境の変化に適応しようとすることでストレスを感じやすくなり、自律神経の乱れを引き起こす要因となります。
体調や気分の変化から「ストレスを感じているな」と気が付いたら、気分転換に適度な運動や深呼吸などを取り入れ、リラックスする時間を意識的に確保してみましょう。
花粉症の影響
春はスギやヒノキなどの花粉が多く飛散し、花粉症の症状に悩まされる方も多いでしょう。くしゃみ・鼻水・目のかゆみがストレスの原因になるだけでなく、倦怠感や頭痛を引き起こしたり、睡眠不足につながることもあります。
食生活の乱れ
春から新生活が始まって急に忙しくなったり生活リズムが変化すると、食生活が乱れやすくなります。栄養バランスが偏ると免疫力が低下し、体調を崩しやすくなります。
日ごろからバランスの良い食事をとる習慣をつけておくことが大切です。
コツコツ取り組む“自律神経を整える習慣”
朝起きたら10分間日光を浴びる
朝に光を浴びることで体内時計がリセットされるといわれており、これによって生活リズムが整いやすくなり、夜に自然と眠りにつきやすくなる効果が期待できます。通勤や通学の時間を活用するのもよいでしょう。
「日光を浴びる」といっても、必ずしも太陽をまぶしく感じるほどの晴天でないといけないわけではありません。意外なことに、曇りの日でも屋外の明るさは約25,000~32,000ルクスと室内(数百ルクス)に比べて圧倒的に明るいため、外に出るだけでも十分な効果があります。雨で外に出られない場合でも、窓際で過ごす時間を作るなどの工夫を取り入れてみてください。
朝1杯の白湯
朝に白湯を飲むことで胃腸が温まり、適度な刺激は内臓の働きを活発にします。これにより、消化機能がスムーズに働き、基礎代謝の向上にもつながります。身体の内側からじんわりと温まる感覚はリラックス効果も期待でき、心身ともに1日の良いスタートを切る助けになるでしょう。
バランスのよい食事
食事をとると、消化のために副交感神経が働きます。主食(ごはんやパン)、主菜(肉や魚)、副菜(野菜など)のバランスと、食後に心地よい満足感を得られる“腹八分目”を意識した食生活を心がけましょう。
また、エネルギー代謝の際に発生する熱によって、身体が温まりやすくなる効果もあります。
楽しく食事をすることは精神的な安定にもつながり、自律神経を整える大切な要素の一つです。
何かと忙しくなりがちな春には、日々のお食事に「筑後産クロレラ」を取り入れることもおすすめ。
クロレラは代謝を助けるビタミンやミネラルを手軽に補給できるだけでなく、おかずの1品としてとらえることで食事の準備に対する負担を減らすことができ、心身ともにサポートする食品として食卓で活躍します。
就寝前の照明にひと工夫
強い白色の光は交感神経を刺激し、覚醒状態から「入眠モード」への切り替えが遅れるため、夜間は避けるのが理想的です。
間接照明やベッドサイドランプなどのアイテムを取り入れ、寝る1~2時間前の照明をあたたかみのあるオレンジ色の光に切り替えることで、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌が促され、自然な眠りにつきやすくなります。さらに、お気に入りの香りや心地よい衣類でリラックスした環境を整えることで、副交感神経が優位になりやすく、より質の良い睡眠に近づきます。

このような毎日のちょっとした工夫が自律神経を整え、心身の健康を支える習慣につながります。
無理なく続けられる方法を取り入れながら、心地よい生活リズムを作っていきましょう。