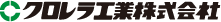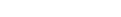クロレラの歴史
1.クロレラ、その開発と研究の歴史
1890年 オランダ人バイエリンクによって発見される。クロロス(緑)とエラ(小さい)を合成してクロレラと名付ける
食糧としての利用 1948〜1963年
第一次世界大戦中のドイツでクロレラを大量培養し、たん白源として利用するアイデアがだされた。第二次世界大戦後にアメリカ、ドイツ、日本で食糧化研究が活発に行なわれた。 東大の田宮博博士らは徳川生物学研究所で屋外大量培養研究を行なった。
- 生産されたクロレラの成分分析、栄養試験、動物試験、安全性試験を行なった。
- カーネギー研究所はベネズエラでライ患者にクロレラを投与、症状が緩和されたと発表、医療的効果の初報告。(1953年)
- (財)日本クロレラ研究所創立、屋外大量培養法が完成する。(1957年) クロレラ抽出液によって乳酸菌の増殖が活発になることが発見される。(1957年)
- NASA発足、宇宙食クロレラが話題になった。(1958年)
- 少量のクロレラ摂取で動物の成長が促進されるとする報告が数多く発表された。(1959年〜)
- クロレラ投与による胃潰瘍の治癒促進効果が発表される。(1962年)
CGF(Chlorella Growth Factor)神話が生まれる。
基礎科学的利用 2度ノーベル賞を獲得
- オット・ワールブルグ博士の光合成研究
- カルビン博士の光合成研究(1961年受賞)
- 現在はDNA解析のために利用されることが多い。
ガス交換体利用 光合成によってCO2を吸収してO2を出す。
- 宇宙船内での利用
- 地球の温暖化防止
1964年 クロレラ工業(株)設立、愛知県豊田市に培養工場を建設、世界で始めての商業的生産を開始する。(東京オリンピック、東海道新幹線開通)
2.公害・薬害と研究が育てたクロレラ
1964年 健康食品「クロレラ錠」発売、健康食品が市場に出始める。公害や食品添加物(着色料)が問題となり始める。
| 年代 | クロレラ関連 | 公害・薬害・環境問題その他行政関連 |
|---|---|---|
| 1953年 | 水俣病が集団的に発生 | |
| 1964年 | 着色料10品目使用禁止 イタイイタイ病発生 |
|
| 1966年 | 難治性創傷の治癒促進効果発表 合成洗剤毒性低減効果を発表 農業疲労に対する効果を発表 |
|
| 1967年 | クロレラの市場開発が進む | 公害対策基本法公布 |
| 1968年 | カネミ油症事件発生 四日市ぜんそく訴訟 水俣病が公害病と認定 |
|
| 1969年 | 学童の発育・発達に及ぼす影響を発表 | 農薬のBHC,DDT製造禁止 |
| 1970年 | 全国スモンの会結成 カドミウム汚染米問題化 |
|
| 1971年 | 厚生省「無承認無許可医薬品の取締まりについて」を通知する。 | |
| 1973年 | カドミウム排泄作用を発表 クロレラブーム始まる |
サッカリン使用禁止 |
| 1974年 | 食品添加物AF-2使用禁止 | |
| 1975年 | ブームとなり類似商品が氾濫 「クロレラ強健法」が出版 |
|
| 1976年 | クロレラブーム絶頂、 200億円の市場に拡大する。 | |
| 1977年 | 他社クロレラによる光過敏症事件発生、ブームに大打撃 | |
| 1978年 | 新聞折込チラシ商法始まる。 コレステロール低下作用発表 |
|
| 1981年 | 抗腫瘍効果を発表 生体防御機能関連研究継続 |
厚生省「クロレラ中のフェオホルバイドの基準値など」を通知する。 |
| 1982年 | 水産用生クロレラを発売 | |
| 1984年 | (財)日本健康食品協会発足、健康食品の規格基準を公示する。 | |
| 1991年 | 厚生省「特定保健用食品制度」を導入する。 | |
| 1994年 | 野本亀久雄名誉教授「免疫と健康」を出版 | |
| 1996年 | 大腸菌O-157食中毒深刻化 | |
| 1997年 | ダイオキシン排泄作用発表 | ダイオキシン汚染深刻化 地球温暖化防止国際会議 |
| 1998年 | 環境ホルモンの影響問題化 | |
| 2001年 | 厚生省「保健機能食品制度」を導入する。 | |
| 緑文字の事例についてクロレラ工業が関与しています。 | ||